早水神社の鳥居をくぐるとまず、早水観音の小さなお社に行き当たります。
早水神社の主な歴史を見ると、「1559年4月 早水観音 神護寺建立」とあり、この場所に神護寺という寺があったことがわかります。現在はお社の中に観音様が祀ってあり、神仏習合といった感じです。神護寺も廃仏毀釈でなくなってしまったのでしょうか。
なんと言っても、観音様ですから、神様ではなくて仏様なわけですが、お社に掲げられている説明文には「境内には観音堂があり縁結び及び安産の神様として昔から近況近在の人々のお参りは絶えません」とあり、神様として崇敬していることがうかがい知れます。
さて、早水観音を通り過ぎると、こんもりとした小山が現れます。説明書きを見ると「県指定史跡 沖水古墳」とあります。
昔は川東からこの辺りにかけてたくさんの古墳があったのだそうです。因みに、都城は古墳がとても多いところです。菓子野町は、時々、茶畑などで古墳が発見され、(畑が陥没して車がはまり発見・・・なんてことも)調査されていることがあります。南九州に多く見られる竪穴式横穴墓(地下式横穴墓)と呼ばれる、いったん縦穴を掘って、そこからさらに横穴を掘り、其の先に玄室を作る(穴の形がL字になるような感じです)古墳です。
また、高崎には円墳や前方後円墳等を、かなり綺麗な形で見ることができます。畑の中に、ぽこぽこ円墳があって実に面白いです。前方後円墳は仁徳天皇陵の縮小版といった感じで形がはっきりとわかります。
こうしてみると、この諸方の地は古墳時代からかなり栄えていたことが想像できますね。










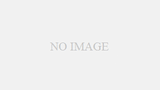
コメント