関之尾といえば滝、そして、世界最大と言われる関之尾甌穴群。
約11万年前、加久藤火砕流でできた溶結凝灰岩の河床に砂粒や歴が穴を穿ち現在もなお形成が進んでいる・・・。うーん、あらためて文章に起こすと、とんでもない物が都城にあるんだなぁと思います。
この地の豊富な水を利用し、開田のための用水路を築いたのが坂元源兵衛。資金不足で途中中断するも、前田正名がその事業を引継ぎ明治34年に前田用水路を完成させます。この用水路の全長は約7㎞(支線も含めると13.5㎞)なのですが、なんとその内の2,6㎞がトンネル。すごすぎます。
ところでこの地に灌漑用水をつくろうとしたのは、これが最初ではありません。1685年というのですから江戸時代の中期、都城領主島津久理(しまずひさみち)の命を受けた家老川上久隆が関之尾滝上流300mに「南前用水」を作っています。さらに、それ以前江戸時代の初期には地元の人たちが滝の下に堰を設け水田に水を引いています。このとき、滝上に祀られた水神様が「出水神様(でみじんさぁ)」。後に、川上久隆が神格化され「川上神社」となります。
関之尾滝の遊歩道に「滝の駅」側から入っていくと、すぐに川上神社が見つかります。出水神様と共に治水に尽力した島津久理、坂元源兵衛、前田正名が祀られており、毎年9月に出水神祭が行われています。
さて、個々までは歴史的なお話。
ここからは、ちょっとオカルトチックに。いろいろな名所と呼ばれるところによくあるのが、「心霊スポット」のお話。
ここ、関之尾滝もご多分に漏れず有名な心霊スポットだそうです。
で、そもそものお話は、昨日今日に始まった話ではなく、今から650年前のお話。ツツジが満開の季節・・・というのですからちょうどこれからの季節、当時の領主本郷資忠(ほんごうすけただ)が、ここで花見をしておりました。このときに呼ばれたのが腰元のお雪(おしず)。酒宴ですので、お酌をして回っておりました。ところが領主の前で緊張してしまったお雪は酒をこぼしてしまい、(都城市公式ホームページ「幸せ上々みやこのじょう」には、”粗酌”と書かれているのですが、辞書で引いてもググってもこの言葉は出てきません。お酌の時に粗相をしたという意味の造語でしょうか)これを恥じて川に身を投じます。お雪には、経幸という恋人がいたのですが、経幸はこのことを嘆き悲しみ、滝の上から日夜お雪の名を呼びます。するとそれに応えるように滝壺から朱塗りの杯が浮かんでくるようになったそうです。
さて、このお話、いくつかのパターンがあり、現在は、「お酒をこぼしたのを恥じて」と書かれている物しか見なくなったのですが、昭和52年に出版された、「宮﨑の伝説 宮崎県民話研究会編」には違う理由が書かれています。お雪さんが、岩から岩へ飛び移りながらお酌をして回っているときにある粗相(お雪山の名誉のためにこの辺はぼかしておきます)をしてしまい、それを酒の入った家臣達にいじられて、耐えきれずに身を投げるという内容になっています。もう一つ、恋人の経幸が「書きおくもかたみとなれや筆のあとまた会うときのしるしなるらん」と岩に刻んで姿を消し、その後朱塗りの杯が浮かぶようになった、という話とお雪の名前を呼んでいたら、それに応えるように杯が浮かんできたという話。個人的には、「宮﨑の伝説」に書かれていたお雪山が身を投げた理由と、経幸が失踪して杯が浮かぶようになったというのがしっくりくるのですが・・・。
いずれ、もっと詳しく調べてみたいと思います。
さて、下の写真は関之尾の遊歩道の途中で撮影した一枚。画像には何のかこうも加えていません。このまんまの風景が目の前に現れて、慌てて写真を撮りました。何というか・・・もののけ姫に出てきそうです。






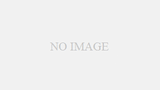
コメント