昨日UPした、「御年神社」のはじめの方で、三股町の神社はすべて参詣したといったことを書いたのですが、すみません、失念していました。三股町蓼池にもう一つ神社がありました。
「早馬神社」です。
蓼池という地区にあり、「竈門神社」と勝岡小学校をはさんで反対側に位置します。都城から296号線を山之口に向かって走り、勝岡小や旭ヶ丘運動公園に行く通りに右折すると左手に早馬神社の鳥居が見えます。
三股で早馬神社と言えば、稲荷神社の隣にある「ジャンカン馬踊り」で有名な早馬神社を思い出しますが、こちらにも早馬神社があります。
とはいえ、信仰の対象となり神社ができたのは明治に入ってからのようで、他の神社と比べると歴史としては浅い神社のようです。
鳥居も、御影石(かな?)の由来書きも立派なものです。写真ではちょっと見えにくいので、由来を書き留めておきます。
|
早馬神社の由来 当神社は 藩政時代 この地域では各戸に耕作用の馬を所有していたので馬供養塚がもうけられ 馬記念が催された 供養塚は中央に塚を築きその上に馬頭観世音菩薩の石像を置き毎年 農閑期(二月、八月、の二回)、集落中の人々が集まり馬の 健康繁殖祈願した 降って明治初年 このような動物愛護の思想は 今一歩進んで信仰となり 供養塚の付近を神域とし 馬頭観音を御神体とする 当早馬神社が創建された 爾来(管理人注_じらい それ以来の意味)牛馬に関する祭典並諸行事が行われてきた 現在霧島を遙かに望むこの景勝の地に位置する当神社は 牛馬の健康繁殖と併せて無病息災 家内安全等に御利役(管理人注_ママ)のある神として尊崇を受けている。 春の祭典 四月三日 夏の祭典 七月二十三日 昭和六十年七月二十一日 |
さて鳥居をくぐると、正面には蓼池の公園が。
公園の一番奥、角の方に神社が見えますがなんだか参道が切られている感じ・・・。ともかく公園を迂回する道路を通っていくと、正面に納骨堂が見えてきました。それを通り過ぎると今度は道が細くなり、車で入っていくと、出るのが大変そうです。とりあえず、納骨堂の前に車を止めさせてもらい、歩いて社殿まで行ってみました。
うーーーん、入り口の立派な鳥居や由来書きに対して、社殿、本殿の方は荒れ果てた感じ。正直、はじめはここが早馬神社とは信じられませんでした。しかし赤鳥居に掲げられていたものなのか、「早馬神社」と彫られた石板が手水鉢の横に立てかけてあるのを見てようやくここに間違いないとわかりました。
社殿に壁はありません。おそらく牛や馬も入れるようにし、健康繁殖を祈ったのでしょう。
ここからは、あくまで個人的な感想なのですが・・・。
それぞれの地域での事情などもあるのでしょうが、この神社は御由緒とは異なり、あまり大切にされている感じを受けませんでした。
参道に関しても、元々大鳥居から社殿まで一直線にあったのではないでしょうか。もしも公園を作るのに参道がなくなったのであれば残念なことです。
早馬神社からの帰り、以前に記事を書いた竈門神社が近かったこともあり、少し遠回りをしていってきました。
新しい年が近くなったからでしょうか、注連縄の垂(しで)が新しく取り換えられており、参道の砂利にもきれいに箒の跡が入っていました。社殿横のポリタンクにも水が入れられ、手を清められるようにしてありました。
ちょっとホッとして家路についた今日の神社巡りでした。







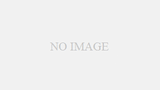
コメント