昨日・一昨日と三股のふるさとまつりに行き、ついでというわけではありませんが、三股の史跡を駆け足で見て回りました。
何というか、三股町の歴史に感心させられた二日間でした。
せっかくなので、少しずつ紹介したいと思います。
最初に紹介するのは「大昌寺跡」。
梶山小学校の山手側にあり、「都城島津三代北郷久秀、忠通」の墓があります。
ここにはかつて梶山城という山城がありました。
時は室町時代前期。時の幕府九州探題今川了俊が少弐冬資を忙殺するという事件が起きます。(水島の変)
原因をざっくり説明すると、九州探題に抜擢され手柄をあげた了俊。その了俊が力を増していくなかで、北朝方で筑前を支配していた冬資はその支配権を了俊に奪われることを危惧し了俊と対立し始めます。この中で起こったのが水島の変です。
この事件が元になり、島津氏・大友氏は了俊に反旗を翻します。こうして、島津氏と今川氏の戦いが始まり、この戦いは応永二年(1395年)まで続くことになります。
水島の変が1375年ですから、20年ほど九州での混乱が続いたということになるでしょうか。
さて、ここからが本題。
当時梶山城を守っていたのは島津方の和田正覚と高木氏。
(二人を梶山城に配したのは北郷義久。久秀の父親です。また、和田正覚は北郷久秀の外祖父に当たります。)
今川方は島津方である和田正覚と高木氏を討伐するために梶山城を攻めます。
これに対して島津氏と北郷義久は、救援として北郷久秀・忠通兄弟を送り込みます。しかし、力及ばず梶山城は落城、北郷久秀・忠通の兄弟も討ち死にしたのでした。
さてこの二人の兄弟の墓が、ここ、大昌寺跡にあるのです。そしてこの大昌寺跡の横にある細い道を上っていくとそこがかつて梶山城のあったところ。
もちろん当時の山城ですから、天守閣のあるようなお城ではありません。
しかし、ここがかつて南九州の覇権を巡る要害の地であり、戦場になったこと、600年の昔、ここで非業の死を遂げた武将の墓が残っていること思うと、歴史の深さを感じずにはいられません。
梶山城がどんなところだったかについてはこちらを。


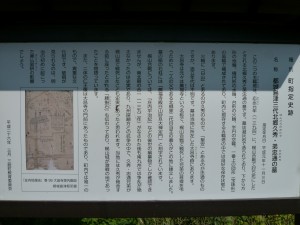









コメント